
松戸市、市川市、宮大工が手掛ける注文住宅・古民家再生の工匠、広報担当です。
皆様こんにちは。
戸建てにお住まいの皆様、ご自宅の屋根の色、どんな建材だったかなどすぐに思い出せますか?建売だったり、先代より住み継いでいたりすると改めて考えたこともなくて一瞬、え?となることがあるかもしれません。これから家を建てようとか古民家再生をお考えの皆様、屋根について具体的なイメージはあるでしょうか。屋根は家を守る役割はもちろん、外観のイメージに大きく関わるものです。
今回は、たくさんある屋根の中でも、日本の景観美を創ってきた粘土瓦葺きの『瓦屋根』の歴史と魅力をお伝えしようと思います。
目次
〇瓦屋根とはとは
〇瓦屋根が日本に伝わった歴史
〇日本三大瓦
〇瓦屋根のメリット
1、優れた耐久性
2、住まいを快適にする性能
・断熱性が高い
・遮音性が高い
3、耐火性
4、豊富なデザイン
〇瓦屋根のデメリット
1、初期費用が高い
2、重い
〇知っていましたか?神社の屋根に瓦は葺かない
〇まとめ
瓦屋根といえば、グレーで重厚感のある屋根。純和風建築を想い描くでしょうか。お寺の大きな屋根やお城を思い出すなんていう方も多いかもしれません。粘土瓦は粘土を一定の形に焼いて作られた屋根を葺く材料です。高い耐久性、防音性、防火性に優れている屋根です。
セメントで作られているセメント瓦というものもありますが、現在の新築にはほとんど使われなくなりました。
瓦は、古代のローマやギリシアで使われていた事が分かっており、とても長い歴史をもつものです。2800年前の中国古代宮殿遺跡では平瓦が発見させています。素材や形、場所によっても様々で、いつ誰によって発明されたのかは明確になっていません。もっともっと古くから瓦と言えるものが存在していたという説もあります。
日本に伝わったのは588年。色々な戦いがありまして、仏教の教えを広めるべく、飛鳥の地に本格的な仏閣を造ることになりました。日本で初めてとなる本格的な仏舎利建設のため、朝鮮半島から様々な技術者と共4に名の瓦作りの技術者(瓦博士)がやってきました。そして、596年に完成したのが法興寺(飛鳥寺)です。日本最古の瓦屋根のお寺です。そして、日本最初の仏教文化が形成されると共に、建築、工芸など大陸からの様々な影響を受けつつ独自の発展を遂げた、飛鳥文化となりました。
仏教の普及とともにお寺が増えていき、その屋根としての瓦の利用が増えていきました。
694年、藤原京の宮殿に寺院以外で初めて瓦が用いられています。平城京や平安京でも瓦が使用されるようになりました。
718年、遷都に伴い法興寺の伽藍の一部が解体され、平城京に再建され元興寺となりましたが、法興寺の瓦が一部再利用されていて1400年以上経っても現存しています。雨、風、太陽にさらされ続ける過酷な環境下でありながら今も尚、耐久性を証明し続けている瓦。当時の瓦博士たちが持っていた技術の高さに驚くばかりです。

▲平城京:元興寺(現存する1400年以上前の瓦)
鎌倉時代になると、戦乱で壊れてしまった寺院の再建のため瓦の需要は高まります。そして、製造技術、施工技術が大きく進歩していきます。
以降、戦国武将が立派な城に瓦屋根を使用するようになり、寺院や宮殿だけのものではなくなりました。今も見ることのできる歴史的城の瓦屋根は本当に美しい景観を作り出しています。

▲姫路城
江戸時代、瓦は、一般庶民には手の届かない高級品でしたし、贅沢も禁止され瓦を使う事は出来ませんでした。ですが、江戸時代末期のころ広く普及していきます。火事の多い江戸の町の防火対策で江戸幕府が瓦屋根を奨励。貸付などもおこないました。
「桟瓦」という軽量化された瓦も考案されて、施工のコストを抑える事にも成功。一般住宅への普及が進みました。
防火対策に最適な建材なんですね。
3つの産地が日本の粘土瓦のシェア8割以上を占めています。ご自宅の屋根が瓦の場合、産地がこの中のどこかである可能性が高いという事です。
三州瓦(愛知県三河地方)
良質な粘土が取れたことと矢作川や良港に恵まれ船便による運搬ができたことにより発展。
洋瓦の技術も取り入れバリエーションが豊富・ハウスメーカーに選ばれ生産量が最も多い産地。
石州瓦(島根県石見地方)
赤褐色が有名。石州で取れる粘土と来待釉薬は高い温度で焼くことができ、耐水性、冷害、塩害にも強い高機能瓦。
雪が多く寒い地域で積極的に使われ広まる。
淡路瓦(兵庫県淡路島)
いぶし瓦が美しい。なめ土という粒子の細かい良質の粘土で造られ、優れた可塑性があり、精度が高い高品質。
いぶし瓦は、表面に炭素膜を作る手法で深い灰色を出す。年月と共に一枚一枚の瓦が色味を変えて、深く渋い風合いの屋根になる。窯変瓦も人気。
どの産地の粘土瓦も共通して耐火性、耐久性、断熱性、遮音性、防水性に優れており、屋根材として大変優秀です。
瓦屋根のメリットとデメリットをまとめます。
1000度以上の高温で焼き上げられる粘土瓦は、夏の日差し、冬の寒さなど環境の変化に影響されにくく、丈夫です。そしてその性能を50年以上持続させることができるのです。塗装もいらない上、劣化した部分だけを吹き替えることも可能な場合があり、メンテナンス費用が抑えられます。
断熱性が高い
立体的に並べられる瓦は屋根との間に空間ができ、その空気層のおかげで夏は涼しく、冬暖かい住環境を保ってくれます。
遮音性が高い
瓦屋根の粘土素材と葺いた後の空気層は外からの音を遮り、暴風や強い雨の音を和らげてくれます。
燃えにくい粘土瓦は、建築基準法で不燃材料として定められています。火災から家を守り、燃え広がるのを防ぐ効果が期待されます。
伝統的な純日本家屋のイメージにとどまることなく、洋瓦の種類も豊富で自分のイメージする家にあう屋根がみつかります。瓦屋根は重厚で高級感もあり、家の表情を豊かにする意匠性の高い建材です。
金属屋根やスレートといった現代において定番の屋根材に比べて初期費用が高くなります。瓦そのものが高価であるのに加えて、専門の職人によが一枚一枚葺いていく工法ですので最初の費用は高くなってしまいます。瓦の耐久性やメンテナンス費用など長い目でトータル的に考える必要があります。
他の屋根材に比べて粘土瓦は重いです。瓦屋根は重くて倒壊しやすい。飛びやすいなどの悪いイメージをお持ちの方がいるかもしれません。重量や昔ながらの工法と支える家の構造は、地震や台風に耐え抜くのことに欠点があったかもしれません。しかし、昭和60年頃から軽くて風にも強い「防災瓦」が登場し、進化して、今では多く製造されています。2000年には、瓦屋根標準設計・施工ガイドラインが制定されました。家の構造自体の耐震性も向上していますから安心して瓦屋根も選択肢に入れてください。
伊勢神宮や出雲大神宮など由緒ある大きな神社の屋根には瓦は葺かれていません。私自身、イメージするところの屋根の形はそれぞれにありますが、瓦か否かは気にとめたことがありませんでした。そこで様々な社寺の写真を見るとなるほど神社の屋根は大半瓦屋根ではない。
理由の一つは、冒頭で触れましたが色々とありまして…仏教を広めるためのお寺を作った際に伝わった屋根の工法だったという歴史があります。仏教建築を倣うことのないようにしていたという説は有力なのかなと思います。
もう一つは、「黄泉の国に神がいることになるから」という説です。瓦の原料は土になりますので、その下というのは黄泉の国という事になってしまうのだそうです。
しかし今では、小さな神社や楼門の屋根に瓦が使われていたりとその考えは柔軟です。
瓦葺きではない神社の屋根もまた、美しいものです。お寺、神社に参拝に行かれた際は、それぞれに立派な屋根を見上げてみてください。

▲東大寺

▲明治神宮
海外でも瓦屋根が美しく街並みを造る有名な場所があります。チェスキー・クルムロフ(チェコ)、コッツウォルズ(イギリス)、ドゥブロヴニク(クロアチア)などです。日本も石州瓦の産地では赤瓦の街並みが美しく残っています。自慢の瓦を載せた家々はとても誇らしそうに見えます。

▲チェスキー・クルムロフ(チェコ)

▲コッツウォルズ(イギリス)

▲ドゥブロヴニク(クロアチア)

▲島根県石見地方「石州瓦」
しかし、瓦屋根は減少していて、たくさんあったであろう美しい瓦屋根の街並みを今はあまり見ることができません。
♪やねより高い~♪から始まる方ではないもう一つの「こいのぼり」の歌に日本の瓦屋根の風景を表す、こんな歌詞があります。
♪いからの波と雲の波
重なる波の中空を
橘かおる朝風に
高く泳ぐやこいのぼり♪
歌詞の中のいからが瓦の意味で、曲線を重なり合わせ並んだ瓦屋根の様子を波に例えているのです。太陽をキラキラと反射する日本家屋の瓦屋根と白い雲の間を優雅におよぐこいのぼりが思い浮かぶでしょうか。

この記事を書き始めて、通りかかったお家の瓦屋根をつい見てしまいます。あの瓦の産地はどこかな?どんな職人さんが何年前に葺いたのだろう。などと考えたりしています。そして、比較的重く強い瓦を敷き詰め、なおかつ50年100年と住継ぐことができる日本家屋や寺院建築は素晴らしい。そして、とてもシンプルに思うのです。歴史深く古いものは素敵だ。こんなお家に守られて、静かにゆっくり和暮らしできたらいいなと想いを巡らせたりしています。
工匠は、千葉県松戸市・市川市を中心に自然素材を活かした古民家再生・注文住宅を手掛けています。
いつまでも丈夫で美しく、愛され続ける住宅をご提供いたします。
家づくりに関するご相談、お悩みなどお気軽にお問合せください。
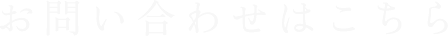

古民家再生を行い、私たちらしい暮らしを叶えたい。

他社で診てもらったら「建て替えた方が」と勧められたが、本当にそうなのか?

予算や間取りなど相談したい。