
松戸市・市川市の魅力や情報を発信していく、地域通信。
皆さんこんにちは。
日本では、今後30年以内に大地震が起こる確率が高いと言われています。また、近年の集中豪雨や大型台風の上陸も防ぐことのできない自然災害です。
地震や集中豪雨が起こるたびに、避難用品を揃えようとか見直さなければと考えます。しかし、平常時には仕事や学校といった日々の生活やイベントの中で頭から消えてしまっていることも多いと思います。災害の事で頭をいっぱいにして、無駄に恐れてばかりもいられません。でも、無関心になってしまってはダメです。かといって、やみくもにあれもこれもと買い揃えてしまうのも違う気がしますね。そこで、皆さんがお住まいの地域にはどのような地形の特徴があり、どのような災害が懸念されているか一度しっかりと調べてみてはいかがでしょうか。まず知っておくことが防災対策の一つになります。
各自治体の防災対策では地形などが細かく分析され、どんな災害が甚大な被害をもたらすのかがシミレーションされてハザードマップになどにまとめられています。そしてしっかりとチェック、更新されながら発信されているはずです。定期的に確認して自分が住んでいる土地のことや災害時にとるべき行動などを把握しておきましょう。いざという時に何もわからないのと、地形や自治体の取り組みを知っているのとでは行動の全てが変わると思います。正しい判断で自分や家族を守ることができるのはもちろん、地域の力になる事ができるのです。

今回は市川市の取り組みの一部をご紹介します。
市川市は、千葉県の西部(チーバくんの口のあたり)に位置しており、江戸川を隔てて対岸は東京都となります。北から東京湾に面している南へ向かってやや傾斜になっています。縄文時代、市川市の半分以上は海の中でした。市内ではかつての沿岸にそって数多くの貝塚が発見されています。海中であった中部と南部は平らな低地となっています。

市川市は利根川水系の江戸川と旧江戸川の最下流に位置しているため、上流のダムと川の水位にも注意が必要です。他にも大小10の河川が市内を通り東京湾へと流れています。そして市川市は、北部、中部、南部とそれぞれ異なる災害が予測されています。住んでいる地域ごとに災害のリスクを確認しておきましょう。

「市川市ってどんなところ?」PDF
→https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/cri05/file/0000448757.pdf
市川市は北部・南部・中部と被害特性が異なります。市内の災害リスクの違いを網羅するべく、市川市では「市川市防災カルテ(小学校区)」というものが作成されています。
そもそもどの地域もなぜ小中学校が避難場所・避難所となっているかというと、大人数の収容、炊き出しが可能などが上げられますが、最大の利点はアクセスの特性です。車が出せなくなる災害時には徒歩での避難となります。基本的に小中学校は子供たちが通えるように数多く点在しています。ほとんどの住民にとって徒歩圏内であり、身近な場所となっているのです。
市川市は市内39小学校全ての区画の防災カルテを作成しています。位置、地形、地域の強み、弱みなどをレーダーチャートでわかりやすく評価しています。小学校区は市川市内を網羅していますから、自分の住んでいる場所を当てはめて、詳しく知ることができます。地域で効果的な対策に取り組むことや住民の意識が高まることで、減災、防災を可能とし、被害を最小限にすることが期待できるのです。
市川市防災カルテ・地区防災計画
→https://www.city.ichikawa.lg.jp/cri03/1111000084.html
「市川市防災カルテ小学校区分」一覧PDF:
→https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000307898.pdf
「市川市防災カルテ小学校区分」カルテ№1 市川小学校PDF:
→https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/cri03/file/0000461720.pdf

▲画像2025/5/15 1/6ページのみ切り取り
市川市では、東日本大震災での課題を解決し、災害対策の強化を図るために女性の視点で防災を考えるプロジェクト(BJ☆プロジェクト)が平成28年に発足しました。女性の視点といっても、女性向けの支援の検討という事ではありません。性別、年齢などによって、被災時に必要なものや困ることは様々なのにも関わらず、必要な支援が行き届かないという課題を解決すべく、避難所運営や支援の対策を検討し、危機管理につなげていくというものです。活動内容を見てみるとその内容は、きめ細やかで被災した地域の全ての人にとってあたたかで親切な提案と改善がなされています。
BJ☆プロジェクトのメンバーは、いくつもの訓練、視察、体験を通し防災や減災について学んでいます。その後、研究と意見交換などを経て、市川市を地域ごとに分析し、防災力の向上につなげています。具体的で解りやすい備蓄品リストが作成され、乳幼児、外国人、ペットへの配慮への提案もなされています。管理栄養士さんが中心となって考えられた、長期保存食を使った「避難所炊き出しレシピ」なんかも発表されています。厳しい状況でも、食べ物がおいしければ元気が出ますから素晴らしいアイディアです。
市川市BJ☆プロジェクト「避難所炊き出しレシピ」PDF:→https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/new01/file/0000419007.pdf
市川市の防災施策に関する提言書PDF:
→https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000248889.pdf
市川市「日頃の備え」BJ☆プロジェクト監修PDF:
→https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000353755.pdf
複数の大きな河川が市内を通り、東京湾に注ぐまでを見届けている市川市は警戒すべき災害の不安要素も多いと感じるかもしれません。しかし、どこに住んでいても予想しきれない自然災害を避けることはできません。だからこそ、地域の防災と減災への取り組みと市民の意識の高さが命を守るために大切なのです。
土地の特性を理解し、細やかな目線をもって、様々な防災対策がなされている市川市は素晴らしいと思います。自治体が備えることで与える安心感は市民の心に余裕を作り、いざという時に冷静な判断ができるようになるのです。
阪神・淡路大震災のときに生き埋めになったり閉じ込められたときに、9割以上の人は、自力または家族や近隣の住民に助け出されたそうです。

内閣府「みんなでつくる地区防災計画」ガイドブックPDF:→https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/pdf/250404_guidebook.pdf
実際に被災地で大きな力になっているのは市民一人一人の助け合いの心と強い気持ちなのです。大きな災害にあったとき、国や自治体が作る安全の中に入っていけるのは第二段階なのかもしれません。でも、大丈夫だと信じさせてくれる地域の取り組みを知っておくことは、自分の冷静さを保ちその場で力を発揮するためにとても大切な、一つの備えになるのだということが分かりました。皆さんも自分が住む地域の取り組みを調べてみてください。防災、減災について多くの備えがされている事が分かると思います。安心につなげると同時に、防災と減災について意識を高めておきましょう。

市川市「防災への備え」→https://www.city.ichikawa.lg.jp/catpage/cat_00140076.html
市川市「災害時におけるペット対策」→https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub01/1111000040.html
千葉県の松戸市、市川市を中心にお仕事させていただき、
このエリアで暮らすご家族が、もっと幸せに暮らせるお手伝いや
地域活性のきっかけになればと想い、スタートしました。
また、エリア外から弊社ホームページを見て頂いた方が
松戸市や市川市を少しでも知っていただく機会になればと思っております。
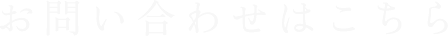

古民家再生を行い、私たちらしい暮らしを叶えたい。

他社で診てもらったら「建て替えた方が」と勧められたが、本当にそうなのか?

予算や間取りなど相談したい。